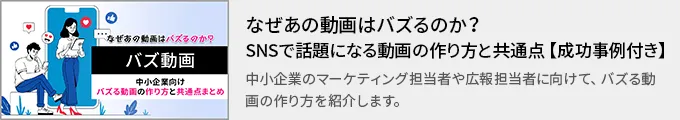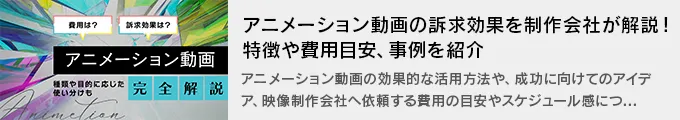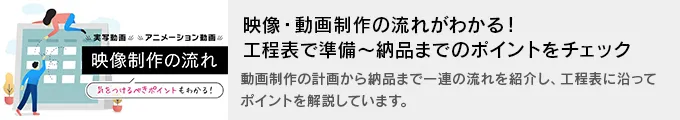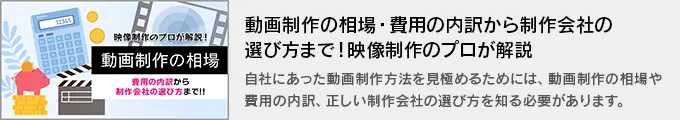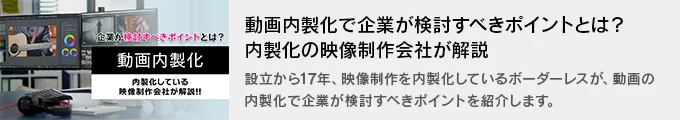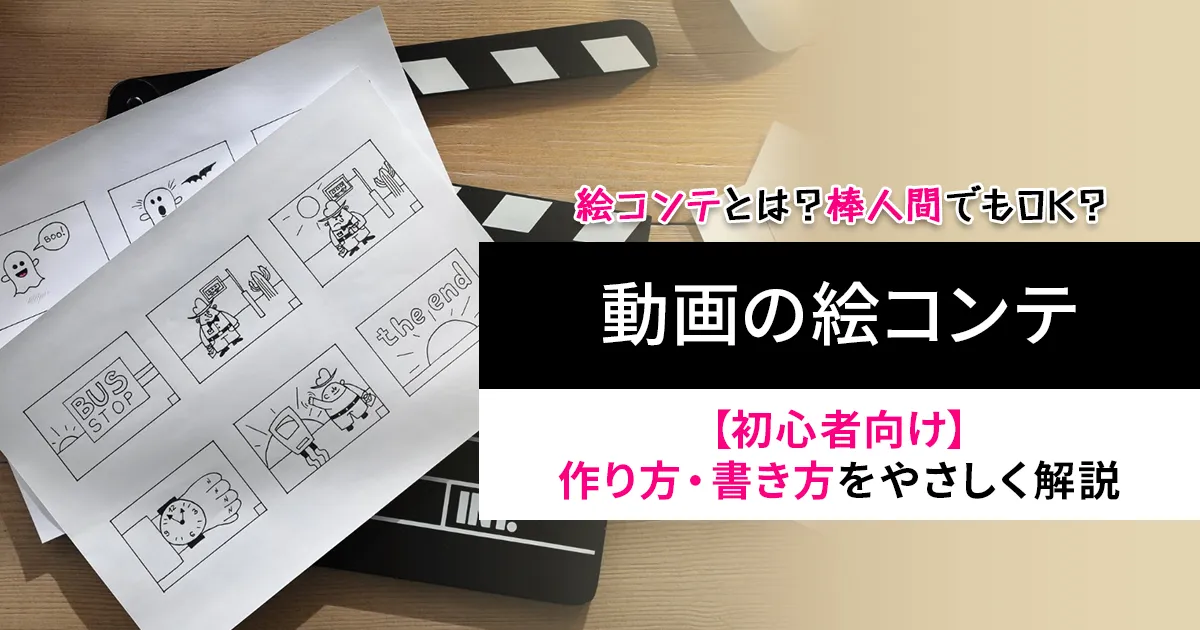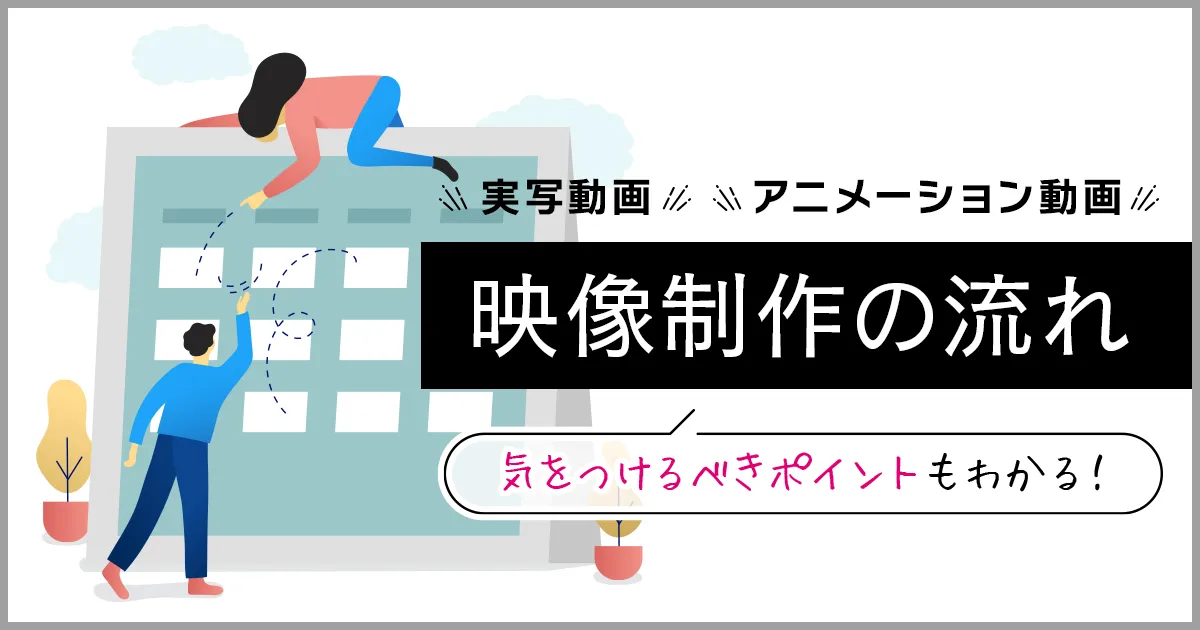動画構成の大切な考え方とは?作り方・フレームワーク・自作するメリットも紹介

2025.08.07
動画構成は、動画の完成度を左右する重要な要素です。適切な考え方で制作する必要があります。
しかし、動画作りに慣れていない方なら
「動画構成はどのような考え方で作ったらいいの?」
「構成でつまずいてしまった…。作り方を教えてほしい!」
「そもそも動画構成は本当に重要なの?」
このような希望や疑問を持つでしょう。
この記事では、映像・動画制作を手掛ける株式会社ボーダーレスが、以下の項目をわかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
- 動画構成の重要性と考え方
- 動画構成の作り方
- 構成作りに役立つフレームワークと事例
- 効果的な動画構成を作るポイント
- 動画構成を自作するときのチェックリスト
- 動画構成を自作するメリット
1. 動画制作で「構成」が重要な理由

適切な考え方で作られた動画構成は、視聴者と動画制作者(企業)にメリットをもたらします。
視聴者のメリット
- 動画の内容がわかりやすい
- 安心して視聴できる
- 最後まで無理なく視聴できる
- 知りたい情報を見つけやすい
動画構成を基に動画を作ると、「誰に、何を、どのように伝えたいのか」が明確になります。こうした動画は、内容がわかりやすく知りたい情報を見つけやすいため、視聴者の高評価につながるのです。
視聴者にとって価値のある動画は、以下のような好循環も生み出します。
-
1. 動画を通じて視聴者のニーズ(欲求)を満たす
-
2.「いいね」「高評価」などが集まる
-
3. YouTubeや検索エンジンなどのアルゴリズムから高評価される
-
4. 検索順位で上位表示される
-
5. YouTubeや検索エンジンなどで「おすすめ動画」として紹介される
-
6. ユーザーとの接点が増える(新規ユーザーの増加・既存ユーザーのファン化)
-
7. さらに視聴回数や高評価の数が増える
-
8. 動画の制作目的(商品・サービスの認知、広報活動、自社のブランディングなど)が達成される
そして、適切な動画構成には「動画制作の余計なコストを防ぐ」「動画作りがスムーズに進行する」といったメリットがあります。
動画構成が決まることで、制作途中の手戻りやムダ撮りが少なくなり余計な人件費・制作費を節約できるでしょう。構成作りは、視聴に喜ばれる動画をムダなく制作する作業です。
動画構成を作らないデメリット

動画構成を作らなかったり雑に作ったりすると、「何が言いたいのかわからない動画」が出来上がるかもしれません。
その結果、以下の状況が想定されます。
- 視聴者が自社の動画をスキップしてしまう(視聴されない)
- 早期離脱が発生する
- 検索順位を獲得できない
動画制作中は、「手戻りやムダ撮りが何度も発生する」「当初の予定より制作期間が伸びた」などのトラブルが頻発するかもしれません。こうした出来事を防止するためには、動画構成に力を入れる必要があります。
2. 動画構成の考え方と具体例

「動画構成=話の順番を並べること」と考える方も多いでしょう。それは間違いではありません。
動画構成では、ターゲット(視聴者)に伝えたい話を伝わる順番に並べ替えることも大切です。
しかし、動画を通じてターゲットに特定の行動を促したいのなら、「視聴者の感情をどのように動かすか」という考え方が重要です。具体的にみていきましょう。
動画構成の具体例

商品・サービスを紹介する動画では、視聴者の悩み・不安に寄り添うパートを作り視聴者の共感を獲得することが重要です。
具体的な方法は次のとおりです。
- 1.「こんなお悩み、ありませんか?」と問いかける
- 2.「お悩みを解決するのに、〇〇がお役に立ちます」と商品のメリットを紹介
- 3. 購入した人の具体例や活用シーンを挿入
- 4. 商品の値段や販売場所、発売日などの詳細情報を提示
視聴者の不安・悩みに寄り添うと、「私の立場を考えてくれている」と相手から共感してもらいやすくなります。共感を獲得できると、続いて紹介する商品の魅力やメリットが印象に残りやすくなるため、動画の目的達成に役立つのです。
反対に、いきなり商品のスペックや機能を説明しても「自分に関係あるの?」と感じた視聴者は間もなく離脱してしまうでしょう。
また、SNSのユーザーは、最後まで視聴するつもりで動画をクリックしません。最初の数秒で価値がないと判断したら次の動画へスキップします。InstagramやTikTok、YouTube Shortsなどでは「動画冒頭の5秒間ほど」で視聴するか・スキップするかを決められているのです。
SNS動画の質を高めるポイント
- 最初の5秒で「これは自分に関係がある」と思わせる
- 伝えたい情報を動画の中盤に配置する
- 動画の終盤にCTA(Call To Action)を設置する
SNSで話題になる動画の作り方や共通点を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▼ 関連記事
3. 動画構成の作り方を4ステップで紹介
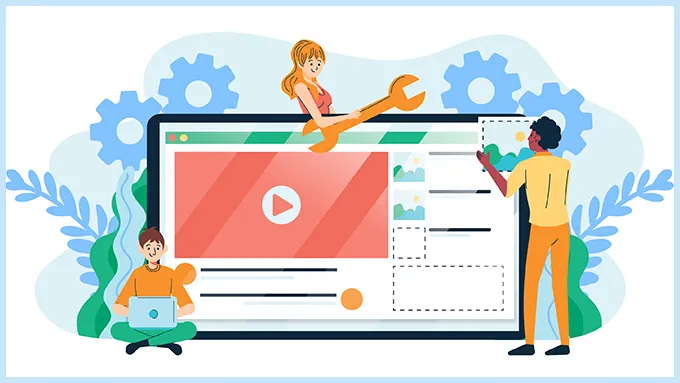
動画構成はどのように作ればよいのでしょうか。動画構成の基本的な作り方を4つのステップに分けて紹介します。
- ステップ1. 「6W2H」を活用して企画案を作る
- ステップ2. 動画の配信場所を決める
- ステップ3. 動画の制作スタイルを決める
- ステップ4. 企画案を基に構成案とシナリオを作る
ステップ1.「6W2H」を活用して企画案を作る

動画構成は、企画を基にして制作されます。企画とは、動画の目的や視聴者(ターゲット)を明確にし、「誰に・何を・どのように伝えるか」を整理する工程です。
目的と視聴者を明らかにして、伝える情報の内容を決めることで、視聴者に正しく伝わる動画に仕上がります。
企画を考えるときは、「6W2H」というフレームワークを活用しましょう。
6W2Hとは、企画書の作成などで活用するフレームワークです。「Why(なぜ)・Who(誰が)・Whom(誰に)・What(何を)・When(いつ)・Where(どこで)・How(どのように)How Much)いくら)で構成されます。企画作りに活用した例が下表です。
| 項目 | 意味 | 考えること |
|---|---|---|
| Why(なぜ) | なぜ動画を制作するか | 動画を制作する理由 |
| Who(誰が) | 誰が動画を制作するか | 制作チーム |
| Whom(誰に) | 誰に向けて動画を制作するか | ターゲット(視聴者) |
| What(何を) | 何の情報を動画で伝えたいか | テーマ・コンセプト |
| When(いつ) | いつ制作するか | 制作期間・スケジュール |
| Where(どこで) | どこで動画を配信するか | 動画を配信する場所 |
| How(どのように) | どのように配信するか | 動画の種類・スタイル |
| How Much(いくらで) | いくらで動画を制作するか | 予算・制作費 |
6W2Hを使って自社の動画企画案を制作してみましょう。
企画によって動画制作の大枠が決まります。大枠が決まると、「何が言いたいか全くわからない動画」が出来上がることはありません。
制作途中で、方向性がブレることも減るはずです。まずは、企画を通じて動画の軸作りに取り組んでみましょう。
ステップ2. 動画の配信場所を決める

動画の配信場所によって、視聴者の特徴や適切な再生時間は異なります。
下表は、YouTube・Instagram・TikTokなどの動画の配信場所・ユーザーの年齢層・再生時間の目安・おすすめの施策をまとめたものです。
動画の目的やターゲットに合わせて、自社に適切な配信場所を探してみましょう。
| 配信場所 | ユーザーの年齢層 | 再生時間の目安 | おすすめの施策 |
|---|---|---|---|
| YouTube | 10代~70代 | 3分~30分(最長12時間、256GBまでの制限あり) |
|
| 30代~70代 | 3分~30分(最長240分、4GBまでの制限あり) |
|
|
| YouTube Short | 10代~70代 | 1分以内 |
|
| Instagramリール | 10代~30代 | 1分以内(最長90秒) |
|
| TikTok | 10代~20代 | 1分以内 |
|
| X | 10代~50代 | 1分以内(最長20分20秒) |
|
ステップ3. 動画の制作スタイルを決める

動画の制作スタイルは、大きく以下の3種類に分けられます。
- ① 実写映像
- ② アニメーション映像
- ③ ハイブリッド(実写+アニメーション)
それぞれの特徴や注意点を確認して、制作スタイルを1つに決めましょう。
| 特徴 | 注意点 | |
|---|---|---|
| 実写映像 |
|
|
| アニメーション映像 |
|
|
| ハイブリッド型 |
|
|
はじめて動画制作に取り組む際は実写映像が多いかもしれませんが、それぞれの特徴や注意点を押さえておくと今後の動画作りがはかどるはずです。
▼ 関連記事
ステップ4. 企画案を基に構成案とシナリオを作る

企画案に基づいて、映像の流れやシーン構成を具体的に組み立てる工程です。
シーンの順序や、各場面で何を見せるかといった、映像の構造を詳細に整理していきます。
続いて、構成案を「シナリオ」に反映していきます。
シナリオとは、構成案をさらに具体化したものです。両者の違いは下表のとおりです。
| 構成 |
|
|---|---|
| シナリオ |
|
また、構成作成の型に「導入・展開・締め」があります。
- ① 導入:動画冒頭の5秒を工夫して、視聴者に「これは自分に関係ある」と感じてもらうパート
- ② 展開:商品のメリット・会社の雰囲気・社員の声などの動画のメインテーマ。具体的に伝える
- ③ 締め:視聴者に具体的なアクションを提示する(応募・問い合わせ・URLをクリックなど)
動画構成を作ったあとの流れ

動画構成を作ると、動画制作は撮影・編集パートに移行します。参考までに、具体的な流れを以下に紹介します。
- ① 撮影準備(撮影スケジュールの策定・撮影場所の手配・キャストの準備・撮影機材の用意など)
- ② 撮影
- ③ 編集・アニメーション制作(素材を適切な長さにカットする・音楽やテロップを加える・必要に応じてアニメーションを作成)
- ④ 完成・公開
映像・動画制作の流れを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▼ 関連記事
4. 動画構成に役立つ5つのフレームワークと制作例
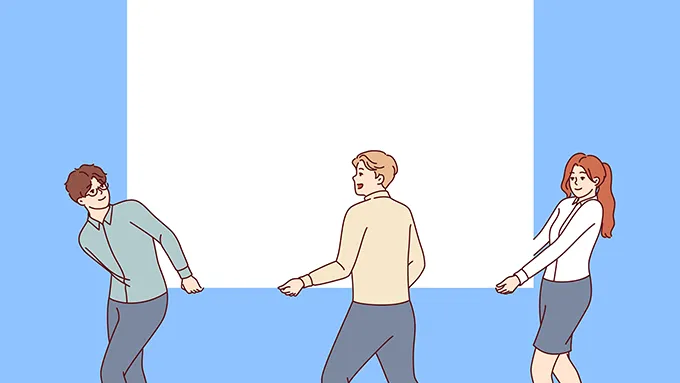
先ほど動画構成作りに役立つ「6W2H」を紹介しましたが、ほかにも構成作りに役立つフレームワークは存在します。5つのフレームワークと制作例を紹介するので、動画構成の参考にしましょう。
- ① 起承転結
- ② PREP法
- ③ CAMS法
- ④ ABCD法
- ⑤ AIBAC法
① 起承転結(きしょうてんけつ)

起承転結は、ストーリー性のある動画を作りたいときに役立つフレームワークです。「導入・背景説明・変化や驚き・まとめのメッセージ」という4つのパートに分けて考えることで、視聴者の感情を動かすこともできます。
起承転結は、会社紹介動画や採用動画、ドキュメンタリー風な動画などを制作するときにおすすめです。
制作例(会社紹介動画・企業ブランディング動画)
| 段階 | 内容 | 具体例(ナレーションやシーン) |
|---|---|---|
| 起(導入) | 主人公の現状を紹介して、視聴者の関心をひく | 「最初は正直、不安だらけでした」 ▶出社風景や通勤シーン・主人公の横顔をカメラに収める |
| 承(背景説明) | 入社した経緯・理由を説明 | 「大学では全く別の分野を学んでいましたが…」 ▶面接の思い出・入社動機・決め手などを紹介 |
| 転(変化・展開) | 実際に働いてみた経験や成長の変化 | 「でも、先輩たちが支えてくれて少しずつ自信がついてきました」 ▶主人公の真剣な表情・仲間とのやり取り・プロジェクトの一場面を挿入 |
| 結(まとめ・伝えたいメッセージ) | 視聴者への共感と呼びかけ | 「次はあなたと一緒に働きたい」 ▶主人公の笑顔・会社ロゴ・エンドカードに「エントリーはこちら」などを設置 |
② PREP法(Point→Reason→Example→Point)

PREP法は、論理的に物事を伝えたいときに有効なフレームワークです。「結論→理由→具体例→もう一度結論」という流れをたどることで、動画に説得力をもたらします。
PREP法は、商品紹介動画や機能説明動画、比較系動画などを制作するときにおすすめです。
制作例(テーマ:クラウド在庫管理ツールの紹介)
| 段階 | 内容 | 具体例(ナレーションやシーン) |
|---|---|---|
| Point(結論) | 最初に伝えたい結論を一言で | 「このクラウド在庫管理ツールを使えば、在庫業務がぐっと楽になります」 ▶商品名+使用画面の映像 |
| Reason(理由) | なぜそれが良いのかを説明 | 「紙やExcelで管理していると、入力ミスや二重在庫などのトラブルが起きがちです」 ▶問題点を描いたアニメーションやイラスト |
| Example(具体例) | 導入事例・使用シーンを紹介 | 「クラウド在庫管理ツールを導入したA社では、在庫管理の時間が月20時間削減されました」 ▶A社の導入シーン・数値データのグラフ・担当者の声(簡易的なもの) |
| Point(再主張) | 最後にもう一度結論を伝える | 「業務効率を改善したいなら、クラウド在庫管理ツールの導入をおすすめします」 ▶CTA(無料トライアル申込・資料請求など)+ロゴ+連絡先情報などを記載 |
③ CAMS法(Catch→Aim→Message→Story)

CAMS法は、相手の注意をひきつけるキャッチーな映像を最初に設置するフレームワークです。動画制作では「視聴者の興味をひく→誰に向けた動画なのか説明する→具体的なメッセージ→メッセージの根拠となるストーリー」という流れをたどります。
CAMS法は、広告動画やWebサイトの導入動画、SNS動画といったスマートフォンで視聴される動画を作るときにおすすめです。
制作例(テーマ:中小企業向け・社内報動画制作サービスの紹介)
| 段階 | 内容 | 具体例(ナレーションやシーン) |
|---|---|---|
| Catch(ひきつけ) | 一瞬で興味をひく導入 | 「社員の顔と名前、ちゃんと覚えてますか?」 ▶表情の乏しいZoom会議や、淡々と進む社内報の紙面映像 |
| Aim(狙いを明確に) | 誰向けの動画かを示す | 「社員数50〜300人規模の企業で、“社内コミュニケーション”に悩んでいる方へ」 ▶オフィスの様子や雑談の少ない職場シーン |
| Message(伝えたいこと) | メインメッセージを端的に伝える | 「社内報を動画で作るだけで、スタッフの距離がグッとつながります」 ▶動画社内報で笑う社員たちのシーン |
| Story(裏付け・理由) | 事例・効果・背景で納得させる | 「導入したある企業は、『社員の声が見える化されて交流が増えた』と感想を述べられていました ▶実例紹介・社員インタビュー・Before/Afterの比較映像など |
④ ABCD法(Attention→Brand→Connection→Direction)
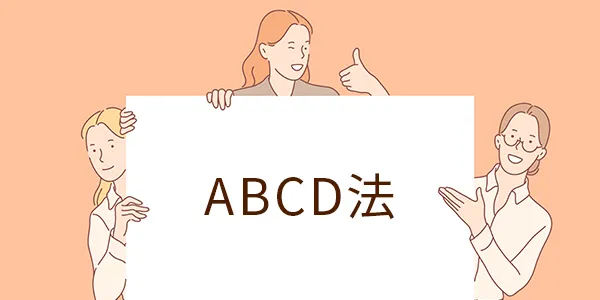
ABCD法は、商品・サービスや企業のブランドを視聴者に印象付けたいときに効果的なフレームワークです。「視聴をひきつける→ブランドの価値を伝える→共感してもらう」という流れを作ることで、視聴者が特定の行動を選ぶ確率を高めます。
ABCD法は、ブランディング動画や企業トップのメッセージ動画などを制作するときにおすすめです。
制作例(テーマ:自社の働き方と価値観を伝えるブランディング採用動画)
| 段階 | 内容 | 具体例(ナレーションやシーン) |
|---|---|---|
| Attention(注目) | 冒頭で視聴者の心をつかむ | 「“働く”って、何のためですか?」 ▶静かな朝のオフィス、出勤前の社員の表情や街の風景 |
| Brand(ブランド紹介) | 企業の価値観・理念・姿勢を伝える | 「私たちは“人を育てること”が最大の投資だと考えています。」 ▶研修シーン、社員同士の対話、経営陣の一言など |
| Connection(共感・関係づくり) | 働く人のリアルな声や共感できるストーリー | 「自分の成長が、会社の成長につながっていると感じます」 ▶若手社員インタビュー、現場での笑顔、オフショット風のやり取り |
| Direction(行動喚起) | 応募・問い合わせなど、次のアクションを促す | 「あなたの可能性を、ここで広げてみませんか?」 ▶「エントリーはこちら」ボタン表示、会社ロゴ+キャッチコピーで締め |
⑤ AIBAC法(Attention→Interest→Benefit→Action→Confidence)
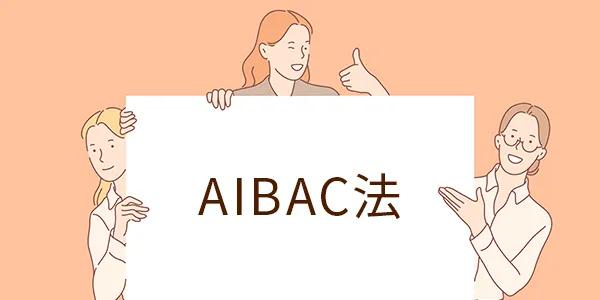
AIBAC法は、信頼性を伝えて視聴者に具体的な行動を促したいときにフレームワークです。「注目→興味→利点→行動→安心感(保証や実績)」という順番で伝えることで、視聴者が納得して購入してもらえる流れを作ります。
AIBAC法は、営業用動画や商品紹介動画、セールス用動画などを制作するときにおすすめです。
制作例(テーマ:中小企業向け 経費精算クラウドサービスの紹介動画)
| 段階 | 内容 | 具体例(ナレーションやシーン) |
|---|---|---|
| Attention(注目) | 最初に視聴者の悩みをピックアップ | 「経費精算、まだExcelでやっていませんか?」 ▶面倒な経費処理にうんざりする社員の演出シーン |
| Interest(興味喚起) | 悩みに共感し、状況を深掘り | 「手作業の入力ミス、承認の手間、経理部の残業…よくある悩みです」 ▶あるあるシチュエーションをテンポよく描写 |
| Benefit(利点の提示) | サービスのメリットを端的に伝える | 「このツールなら、経費精算が3ステップで完了。月10時間の工数削減に」 ▶ UI画面の操作カット・導入効果のグラフ表示 |
| Action(行動喚起) | 次のアクションを明確に | 「まずは無料トライアルから始めてみませんか?」 ▶CTAボタン・URL・電話番号などの表示 |
| Confidence(信頼づけ) | 実績・保証・安心材料を伝える | 「導入企業1,500社以上。サポート体制も充実しています」 ▶ロゴ一覧・導入企業のコメント・サポートスタッフの対応シーンなどを挿入 |
なお、フレームワークをすべての動画構成に当てはめる必要はありません。フレームワークに当てはまらないからダメな構成、ではないのです。フレームワークは、「伝えたいことを、どう整理すれば伝わるか」を考えるヒントとして気楽な気持ちで使用してみてください。
5. 効果的な動画構成を作るポイント

効果的な動画構成を作る5つのポイントを紹介します。
- ① まず“型”に当てはめる
- ② 構成を作る習慣を持つ
- ③ 第三者からフィードバックをもらう
- ④ 冗長なセリフや説明を短くする
- ⑤ 動画構成を作成するタイミング
動画制作が初めての方にも役立つ情報を紹介するので、一つずつみていきましょう。
① まずは“型”に当てはめてみよう
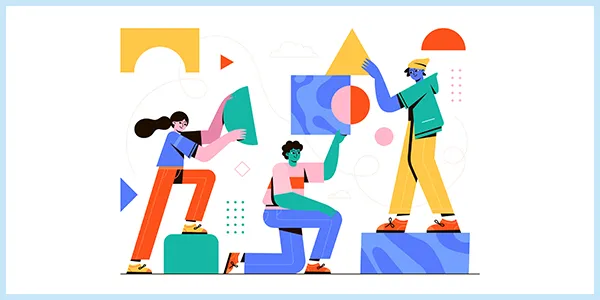
動画構成に自信のないときは“型”に当てはめることから始めましょう。先ほど紹介した「起承転結」「PREP法」「CAMS法」などのフレームワークに当てはめるだけでも、動画構成は整理されます。
ポイントは、動画の構成やターゲットに合った型を使うことですが、まずは1つの型で構成案を作ってみましょう。採用動画に「起承転結」を当てはめてみたり、商品紹介動画に「PREP法」を活用したりして、自社に合った方法を探してみてください。
② 構成を作る習慣を持つ

「完璧な構成を作らなきゃ」と思わずに、まずは構成を作る習慣を持つことが大切です。繰り返し構成を作るうちに、「こうすると伝わりやすいかも」「視聴者にひびく言い回しってこれかな?」といった勘が働くようになります。こうした経験が構成作りの技術を高めるのです。
構成は、用意するだけでも社内にメリットをもたらします。社内の情報共有や外注先とのやり取りがスムーズになるのです。構成案を作成するだけでもメリットがあると捉えて、まずはできることからスタートしましょう。
③ 第三者からフィードバックをもらう

作った構成案を第三者にみてもらう方法もおすすめです。率直な評価や改善点を知ることで、「動画の内容がわかりやすいか、興味をひかれるか」を客観的にチェックできます。
せっかく動画構成を作るなら、自社の魅力や強みを余すところなく伝えたいですよね「あれも伝えたい!」「これは外せない情報だ」と情報を盛り込みたくなるのも無理はありません。ですが、メッセージをいくつも組み込むと、かえって肝心なことが伝わりにくくなります。
第三者の視点をいかして、より視聴者に伝わる動画構成を作成しましょう。
伝わる動画構成のポイント
- 視聴者が知りたいことを軸に組み立てる
- 伝えたいことは1つに絞る
- 他部署の人・友人や知人・家族などの第三者から客観的なフィードバック(評価と改善点)をもらいやすい
④ 冗長なセリフや説明を短くする
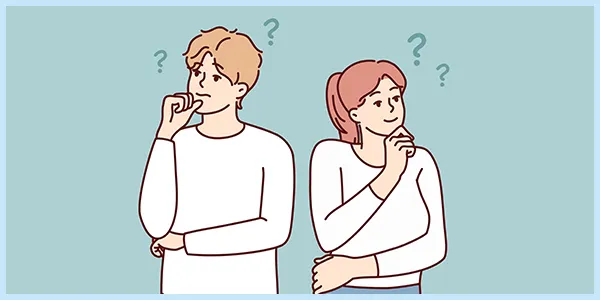
冗長とは、文章や話が必要以上に長かったり意味が重複したりして、ムダの多いことです。冗長は視聴者からの低評価を招くおそれがあります。
例を挙げてみましょう。「構成作りで、最初にやるべきことは、企画案をあらかじめ作成しておくことです」という表現が冗長にあたります。ムダを削いで、「構成作りで最初にやることは、企画案の作成です」でも意味は通じるでしょう。
動画制作でも、セリフや説明の冗長を避けましょう。セリフや説明は、シナリオに記載することが多いと思います。シナリオの段階で冗長をカットすると、視聴しやすく伝わりやすい動画になります。シナリオを作らない場合は、構成の段階で冗長をカットしましょう。
⑤ 動画構成を作るタイミング
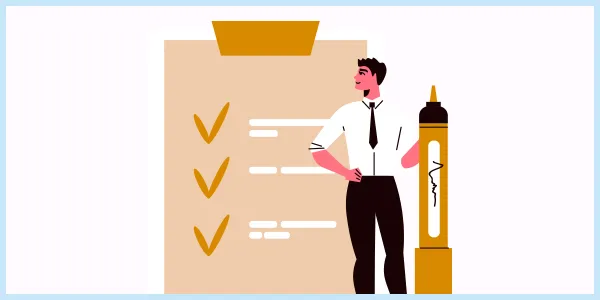
動画構成を作るタイミングは、企画を制作したあとです。企画の内容に基づいて動画構成を作ることで、伝わる動画の基礎ができます。
「企画→構成」の手順を踏まないと、手戻りやムダ撮りが頻発するかもしれません。余計なコストを防ぐために、動画構成を作るタイミングに注意しましょう。
6. 動画構成を自作するときのチェックリスト

動画構成を自社で作るときは、「自分たちよがり」にならないことが大切です。以下のチェックリストを参考にして、会社目線になりがちな動画構成を「視聴者目線」に変えていきましょう。
視聴者目線の動画構成になっているかを確かめるチェックリスト
- ① 会社の歴史や沿革ばかり語らない
- ②「代表・社長からメッセージだけ」で動画の半分を占めない
- ③ 社内用語や業界用語をそのまま使わない(注釈をつけたりわかりやすい言葉に言い換えたりしましょう)
- ④「視聴者が知りたいこと」を伝えてから「自社が伝えたいこと」を述べる
- ⑤ 動画の目的(応募・問い合わせ・認知獲得など)に沿って作る
- ⑥ 視聴者の興味をくすぐるような仕掛けを設ける(動画冒頭にあるのがベストです)
動画の大きな目的は、自社に利益をもたらす行動を視聴者に促すこと。視聴者のニーズを満たしたあとに、視聴後に取ってほしい行動を提示しましょう。
「問い合わせボタンをクリック」「アカウントをお気に入り登録してください」「ぜひ購入ください」といった内容を提示すると、その行動を取ってもらいやすくなりますよ。
7. 動画構成を自作するメリットは「外注コストを抑えられる」こと

動画構成を自社で制作する大きなメリットは、外注コストを抑えられることです。以下に、動画・映像制作を10,000本以上の制作実績を持つ弊社が、外注コスト削減の理由を解説します。
動画制作で構成案が占める割合

構成案の制作は、制作会社の予算(企画構成費)の大部分を占める項目です。依頼企業へのヒアリング、ヒアリング後の構成案作成作業には多くの時間や人手がかかります。
そのため、構成案を自作して制作会社に渡すと制作会社の作業工程は短縮されます。制作会社からみれば、「あとは撮って編集するだけ」となるのです。構成案の完成度が高ければ、より初期費用を抑えられるでしょう。見積もり金額もリーズナブルになります。
動画制作費の相場や費用の内訳を知りたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。
▼ 関連記事
どこまで社内でやって、どこからプロに任せるべきか

それでは、動画構成のうち、どこまでを社内で行いどこからプロに任せるべきでしょうか。
動画構成で自作できる項目とおすすめ度、ポイントを下表にまとめたのでご確認ください。
| 項目 | おすすめ度 | ポイント |
|---|---|---|
| 動画の目的・ターゲットの設定 | ◎ |
|
| 構成案の作成 | ◎ |
|
| シナリオ作成(セリフやナレ) | △ |
|
| 撮影・編集 | ✖ or △ |
|
| ナレーション・BGM・演出 | ✖ or △ |
|
動画構成を自作すると自社にも制作会社にもメリットがある

動画構成を自作する大きなメリットは制作費用を抑えられる点ですが、他にも以下のようなメリットがあります。
- 制作会社とのやり取りがスムーズになる
- 動画の方向性がブレない
- 手戻り・方向修正の発生を最小限にできる
- 修正すべきポイントを早期発見できる
- 社内の動画への理解が深まる
構成作りは、動画のコストカットだけでなく動画の質を高めます。動画の成功確率を上げる投資といってよいでしょう。
ただし、すべての作業を内製化するのは負担が大きいため、「動画構成を考えるのは自社」「形にする工程はプロに任せる」という選択がベストです。自社の予算や体制、目標達成の難易度などに合わせて、ぜひ最適なスタイルをご検討ください。
動画内製化で企業が検討すべきポイントを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▼ 関連記事
8. まとめ|動画構成は「設計図」づくり。ここから始めよう
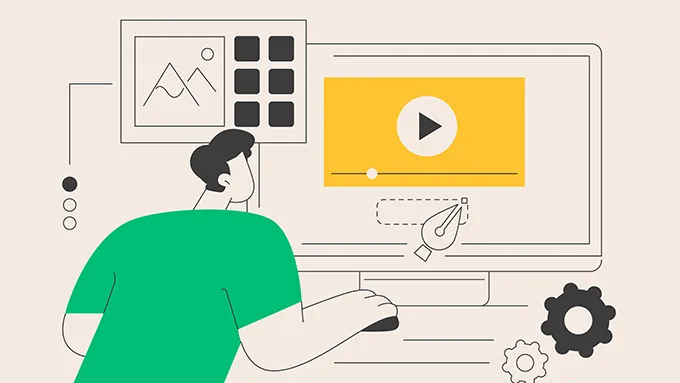
動画構成は、動画制作の序盤で行う作業にも関わらず、全体の完成度を左右する項目です。制作の際は、映像の順番だけでなくどのように伝えるかまで設計するため、目的と伝えたい内容をつなぐ橋のような存在を作っているともいえるでしょう。
撮影や編集の前に構成を固めておくことで、制作の意図が明らかになり、動画のムダ撮りや手戻りを最小限にできます。何より構成が整理された動画は、「何が言いたいかわかる」「検討しやすい」と視聴者の高評価につながり、最終的に自社の利益拡大に役立ちます。
動画構成につまずいた方、制作した動画が思うような成果を出せなかったときは、ぜひ本記事を見返してみてください。効果的な動画構成を作り、視聴者に求められる動画を制作しましょう。